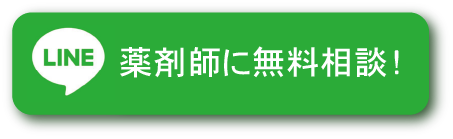date:
03.2023.03漢方で紐解く「涼感・涼性」と「溫感・溫性」の違い:あなたの不調、もしかして「体質」のせいかも?
漢方でよく耳にする「涼感(りょうかん)」「涼性(りょうせい)」「溫感(おんかん)」「溫性(おんせい)」という言葉。なんだか難しそうで、どう違うのかよく分からないと感じていませんか?
実は、これらの言葉は、あなたの身体の不調を理解し、毎日の生活をより快適にするためのヒントがたくさん詰まっているんです。今回は、40 代以上の身体の痛みや不調にお悩みの方に向けて、これらの言葉が何を意味し、どのように役立つのかを分かりやすく解説していきます。
「涼感」と「涼性」はどう違うの?
まず、「涼感」と「涼性」について見ていきましょう。
**「涼感」** は、例えば暑い夏に冷たいアイスクリームを食べたり、キンキンに冷えた水を飲んだりした時に感じる、あの「ひんやり気持ちいい感覚」のこと。これは、誰もが感じる主観的な感覚ですね。
一方、**「涼性」**は、漢方でいう「薬の性質」を表す言葉です。身体の熱を冷まし、炎症を鎮めたり、解毒作用があるといった性質を持つ生薬や食品を指します。代表的なものには、菊花(きくか)、大黄(だいおう)、**石膏(せっこう)**などがあります。
これらの涼性の生薬は、熱っぽい時、炎症がある時、身体に余分な熱がこもっている時など、「熱」が原因で起こる症状の改善によく用いられます。
「溫感」と「溫性」はどう違うの?
次に、「溫感」と「溫性」の違いです。これも「涼感」と「涼性」と同様に、主観的な感覚と生薬の性質の違いを指します。
**「溫感」** は、寒い冬に温かいお味噌汁を飲んだり、お風呂にゆっくり浸かったりした時に感じる「じんわり温まる心地よさ」のこと。これもまた、誰もが感じる主観的な感覚です。
そして、**「溫性」**は、漢方でいう「薬の性質」で、身体を内側から温め、元気や活力を補い、血行を促進する性質を持つ生薬や食品を指します。例えば、人参(にんじん)、当帰(とうき)、**肉桂(にっけい)**などがこれにあたります。
これらの溫性の生薬は、冷え症、胃腸が弱い、疲れやすい、貧血気味など、「冷え」や「不足」が原因で起こる症状の改善によく用いられます。
漢方における「涼性」「溫性」の役割
まとめると、「涼感」と「溫感」はあなたの感覚、「涼性」と「溫性」は生薬や食品が持つ性質を指します。
漢方では、身体に熱がこもっている「熱証(ねつしょう)」の状態には「涼性」の生薬で熱を冷まし、身体が冷えている「寒証(かんしょう)」やエネルギーが不足している「虚証(きょしょう)」の状態には「溫性」の生薬で身体を温め、補うという考え方で治療を行います。
ご自身の身体が「熱っぽい」と感じるなら涼性のものを、「冷えている」と感じるなら溫性のものを摂ることで、身体のバランスを整え、健康維持に役立てることができるのです。
日常生活での「涼性」「溫性」の活用法
この「涼性」「溫性」の考え方は、漢方薬だけでなく、普段の食事にも活かすことができます。
例えば、暑い夏には、身体の熱を冷ます涼性の食材であるスイカ、冬瓜(とうがん)、クワイなどを積極的に摂るのがおすすめです。
一方、寒い冬には、身体を温め、エネルギーを補給してくれる溫性の食材である生姜(しょうが)、なつめ、**山芋(やまいも)**などを取り入れると良いでしょう。
漢方と西洋医学の「冷え」「熱」は違う?
ここで一つ大切な注意点があります。漢方でいう「涼性」「溫性」は、西洋医学の「冷たい」「熱い」とは少し意味合いが異なります。
西洋医学でいう「冷たい」「熱い」は、文字通り「温度」を指しますが、漢方では、身体の「状態」や生薬・食品の「性質」を表す言葉として使われます。
そのため、漢方薬や漢方を取り入れた食事療法を行う際には、ご自身の体質やその時の症状に合わせて、最適な方法を選ぶことが重要です。自己判断せず、専門の医師や薬剤師、栄養士などの指導のもとで取り入れることをおすすめします。
「涼性」「溫性」を裏付ける科学的根拠
漢方における「涼性」「溫性」の概念は、経験則だけでなく、近年の研究によってそのメカニズムが徐々に解明されつつあります。
例えば、『中国医学ジャーナル』に発表された研究では、涼性の生薬には植物アルカロイドやサポニンといった成分が多く含まれ、これらが清熱解毒作用や潤燥養陰作用(身体に潤いを与え、陰のバランスを整える作用)を通じて身体の機能を調整することが示されています。
また、溫性の生薬には揮発性油や粘液質といった成分が多く含まれ、これらが身体を温め、寒さを取り除き、血行を促進する作用を通じて身体の機能を調整することも分かっています。
さらに、『食品研究開発ジャーナル』の研究では、食品の「涼性」「溫性」もその栄養成分や作用メカニズムに関連していることが指摘されています。涼性食品にはビタミン C、 カリウム、カルシウムなどが豊富で、熱を冷まし、喉の渇きを潤し、炎症を鎮める効果が期待できます。一方、溫性食品にはタンパク質、脂質、****糖質**などが含まれ、これらが気(生命エネルギー)や血(血液)を補い、身体を温める効果に繋がるとされています。
これらの研究結果は、漢方における「涼性」「溫性」の概念が、科学的な根拠に基づいていることを裏付けています。
まとめ:あなたの健康に「涼性」と「溫性」を活かそう
「涼感」「涼性」「溫感」「溫性」は、漢方において、主観的な感覚と生薬や食品の性質を区別し、身体のバランスを整える上で非常に重要な概念です。
これらの知識を日々の生活や漢方治療に取り入れることで、あなたの身体に合ったセルフケアができ、より良い健康状態を保つことに繋がります。
当社の漢方商品は、これらの「涼性」「溫性」の考え方に基づき、厳選された生薬を配合しています。もし、あなたの身体の不調が、もしかしたら「冷え」や「熱」によるものかもしれないと感じているのであれば、ぜひ一度、当社のウェブサイトをご覧になってみてください。
【お問い合わせ先】 当社の漢方商品にご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。 代理店・販売店としてご検討されている企業様からのご連絡も心よりお待ちしております。 詳細については、[お問い合わせページへのリンク] をご覧いただくか、直接ご連絡ください。